2005年1月24日(月)
** 甘樫丘・高松塚古墳 **
10:50 天王寺・近鉄急行(\610-) 11:30 橿原神宮前 12:35 甘樫丘・豊浦(toyura)展望台:昼食
14:40 高松塚古墳 15:57 飛鳥駅着 16:25 飛鳥(急行\690-) 17:15 天王寺

|
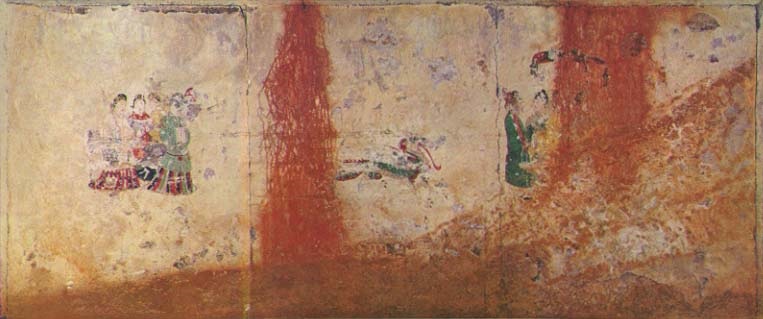
|

|
[大和古代ニュース] |
||
|---|---|---|
「豊浦宮」の石敷き 再び -明日香村- | ||
●明日香村豊浦の向原寺境内● 明日香村豊浦の向原寺(こうげんじ)境内で、女帝・推古天皇が592年に即位した豊浦宮(とゆらのみや)跡とみられる石敷き遺構が奈良文化財研究所の調査で出土。現地で23日、説明会があった。石敷き遺構の確認は85年調査に次いで2カ所目。豊浦宮の可能性が高まった。石敷き遺構の上層では、国内最古級とされる豊浦寺創建時の、講堂の基礎部分を確認。豊浦寺の講堂が南北18メートル以上の規模だったとわかった。 豊浦宮の石敷きと豊浦寺講堂跡の遺構は、向原寺境内の北側に納骨堂を建立するための事前調査で約14平方メートルというごく狭い面積を発掘して見つかった。 地表面から深さ1・2メートルを掘り下げ、版築(はんちく)と呼ばれる、土をつき固めた基礎部分が出土した。豊浦寺講堂の基壇跡とみられる。85年に同研究所が向原寺境内の約10メートル南側で確認した講堂の基壇跡や柱穴遺構と同じ層だった。 さらに版築層を南北3・8メートル、東西30センチの細長い範囲で約50センチ掘り下げると、小石を敷き詰めた遺構が出てきた。調査担当の小沢毅・同研究所主任研究官は、この石敷きが85年の調査で確認された豊浦宮の遺構と判断。「豊浦宮の面的な広がりが見えてきた」と話す。 また、豊浦宮上層の豊浦寺講堂の基礎部分が確認できたことで、85年の確認位置から計算して、豊浦寺の講堂が南北18〜22メートルの規模だったことがわかった。版築層は北側が中世に削られているため北側への広がりを確認できなかったが、国内最古の寺院とされる同村の飛鳥寺(6世紀後半)の講堂(南北約23メートル)に匹敵する可能性もある。 23日の説明会には、地元の人や考古学ファンら約30人が参加した。小沢主任研究官が色の違う地層を示しながら、基壇跡や下層の豊浦宮の石敷きを解説。「飛鳥寺に匹敵する可能性も」「推古天皇にふさわしい建物」などの説明に、見学者は遺構を眺め聴き入った。 日本書紀などによると、推古天皇は豊浦宮で即位後、近くの小墾田(おはりだ)宮に移る。その際、豊浦宮を譲り受けた蘇我馬子が豊浦寺にしたという。 ●大脇潔・近畿大教授(考古学)の話● 大きな石を広く敷き詰めた天武天皇の飛鳥浄御原宮に比べ、豊浦宮は西に山が迫り、東に飛鳥川が流れる狭い地形で、小石を建物の周りにだけ敷いた小規模な宮殿だったことがわかる。飛鳥の宮殿の、最初の段階が見えてきた。 | ||
| (2004/10/24) |
15:15 国営飛鳥歴史公園館 15:45
石人像・須弥山石 は 石神遺跡から出土、現在それらのレプリカは 飛鳥資料館 にあるらしい。
これらは噴水用として使われたと推測されている。酒船石や亀形石造物:水路、流水の演出?
